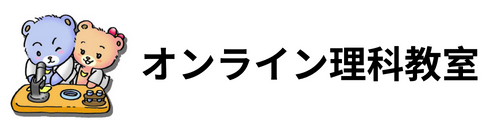4年(上)
第1回 磁石
1.磁石
2.磁石の性質
3.磁石を作る
4.電磁石
すべて磁石・電磁石。
磁石(基本)と磁石(磁力線)を見ておけば十分。演習問題集の練習問題3の筋道を立てて考える問題も解けるようにしよう。
第2回 昆虫
1.昆虫のからだ
2.モンシロチョウの成長
3.昆虫の成長の仕方
4.昆虫に近い仲間
5.いろいろな動物
すべて昆虫。
「アゲハとモンシロチョウ」「昆虫①」「昆虫②」を見ておこう(特に「昆虫①」)。演習問題集は発展問題も重要。
第3回 流れる水のはたらき
第4回 季節と天気
1.天気
2.季節と天気
3.気象の観測
天気の基本。演習問題集の練習問題が解ければOK。授業動画は、風と気圧・天気と湿度の「天気の変化」。また、台風について、やや細かく問われる。「台風はなぜ成長するの?」も、勉強になる。
第6回 春の生物
1.春になると
2.花をさかせる植物
3.芽を出す草
4.昆虫
5.いろいろな動物
春の植物がポイント。授業動画は、季節と生物の「早春の植物」「桜のころの生物」「春後半の生物」を見ておこう。暗記カードも、載せておいたので、覚えるのに使ってね。
第7回 太陽
1.太陽と地球
2.太陽の動き
3.太陽の位置の表し方
4.地面にできる影
太陽高度と季節の日陰曲線で応用問題が出る。授業動画は、太陽と地球の「太陽と気温」「太陽と影の動き」を見ておく。「なぜ春分の日の影が直線になるのか?」の動画も、勉強になる。
第8回 水のすがた
1.水の蒸発
2.水の沸とう
3.水と氷
4.水の3つのすがた
5.地球上をめぐる水
授業動画は、水と氷と水蒸気・三態の「水と氷の不思議」「水のあたたまり方」。演習問題集の練習問題3は重要。次の2つの式を使って、解けるようにしておく。1つは、全降水量=全蒸発量。もう1つは、陸から海の水の移動=海から陸へ恩水の移動。
第9回 光
1.光
2.はね返される光
3.曲げられる光
授業動画は、鏡・光・レンズの「鏡と潜望鏡」「光の性質と針穴写真機」あたり。演習問題集の練習問題3のレンズ問題は、「レンズの応用」の冒頭に実際の実験がある。鏡の入射角、反射角の計算は、よく出る問題にある。
第11回 植物の成長
第12回 植物のつくりとはたらき
1.植物のつくりとはたらき
2.植物のつくり
3.植物のはたらき
授業動画は、植物の「光合成」「植物(水の通り道・蒸散)と顕微鏡」。光合成の実験で、なぜ、湯・アルコール・水につけるのか、意味を把握しておくこと。
第13回 身のまわりの空気と水
1.身のまわりの空気と水
2.空気や水の重さ
3.空気や水をおし縮める
4.空気や水の体積と温度
5.空気や水のあたたまり方
授業動画は、とじこめられた空気と水の「①②」。温度と体積の「膨張と収縮(空気と水)」。
第14回 金属
第16回 夏の生物
1.夏になると
2.花をさかせる植物
3.実をつける植物
4.昆虫
5.いろいろな動物
授業動画は、季節と生物の「夏の生物」。昆虫は、カブトムシとセミとシオカラトンボについて、卵や幼虫のようす、何を食べているかなど、まとめておこう。
第17回 星座をつくる星
第18回 星座の動き
第19回 動物
5年(上)
第1回 季節と生物
1.季節と植物
2.季節と昆虫
3.季節と動物
範囲が広い、知識の総まとめ単元。全体をじっくりやる余裕はないので、演習問題集の基本問題・練習問題を解いて、理解があいまいになっている部分を、メイン教材で振り返るのが効率よい。
授業動画はすべて、季節と生物。特に、「冬越し」と「春の生物(早春の植物・桜のころの生物・春後半の生物)」と「鳥」が重要。
第2回 物の温度による変化
1.物の状態
2.物の状態と体積
3.空気の温度と体積
4.水の温度と体積
5.金属の温度と体積
テーマは2つ。1つは。水を冷やしたり加熱したりするときの変化。もう1つは、空気や水や金属の、温度と体積の関係。
授業動画は、1と2と3は、水と氷と水蒸気・三態。「水と氷の不思議」「物質の三態」「水のあたたまり方」を見ておこう。特に、水をあたためた時に出る2種類のあわ(最初に空気、最後に水蒸気)は重要。4と5は、温度と体積(膨張と収縮)。演習問題集の練習問題1は、必ずテストに出ます。
第3回 物のあたたまり方
第4回 季節と星座
1.星座と星
2.四季の星座
3.星の日周運動
4.星の年周運動
5.星座早見
授業動画は、星の「夏の星と流星群」「冬の星」「星座早見」「星の動き」。基本星座を覚えること。また、同じパターンだけなので、星の動きの計算ができるようにしよう。よくある問題の「星の動き」を活用しよう。
第6回 気象の観測
1.気温と地温
2.雲と雨
3.風向・風速・風力
4.しつ度
授業動画は、風と気圧・天気と湿度の「太陽と気温」「湿度」。風向は「風と台風」にある。
第7回 天気の変化
1.天気をつくりだすもの
2.気圧と風
3.気団と前線
4.天気の変化
授業動画は、風と気圧・天気と湿度の「風と台風」「天気の変化」「温暖前線・寒冷前線」。
第8回 てこと輪軸
第9回 植物のつくり
1.植物の分類
2.根のつくりとはたらき
3.茎のつくりとはたらき
4.葉のつくりとはたらき
授業動画は、植物の「植物(水の通り道・蒸散)と顕微鏡」と「植物の根・くき・葉のはたらき」「水草の光合成と葉序」にある。植物の根・茎・葉のつくりを、双子葉と単子葉で整理しておく。また発展問題の葉序は、上記動画を見ればスッキリわかると思う。
第11回 植物の成長
1.種子のつくり
2.種子の発芽と成長
3.花のつくりと受粉
4.いろいろな花
5.果実
授業動画は、植物の「種子のつくりと発芽成長の条件」と「花のつくり①②」
花の分類がなかなか大変だけど、双子葉は花びら(がく)・おしべが5の倍数、単子葉は3の倍数と、原則を理解して、最後に例外を補足しておくとわかりやすい。余裕があれば、YouTubeの「花のつくりと分類①~③」も観ると勉強になる。
植物の根・茎・葉のつくりを、双子葉と単子葉で整理しておく。また発展問題の葉序は、上記動画を見ればスッキリわかると思う。
第12回 水溶液の濃さ
1.水溶液
2.溶解度
3.水溶液の濃さ
4.溶質の取り出し方
授業動画は、溶解度の「物の溶け方(溶解度)」とよく出る問題の「溶解度計算全パターン」。
演習問題集の基本問題ができれば、それでかなり得点力はついている。余裕があれば、練習問題→発展問題。
この単元は、「いくらやってもできない」と思ったら、保留してOK。不思議なことに、1年たつと、自然とできるようになる。よく「どうして5年のときはできなかったんだろう」と子ども自身が言う。
第13回 物の運動
1.ジェットコースターの運動
2.ふりこの運動
3.ふりこのおもりがぶつかる力
4.斜面を転がるための運動
5.慣性の法則
授業動画は、振り子と運動の「ふりこ」「運動ー速さ」「運動ー衝突」「運動(慣性・自由落下・放物」。
内容が濃すぎ。演習問題集の練習問題2の振り子の長さと周期の計算、練習問題3の水平打ち出しの計算は重要。
第14回 太陽系の天体
1.いろいろな星
2.月の満ち欠け
3.月の出入りと南中
4.月の動き
5.月といろいろな現象
授業動画は、月の「月①②」とそれに続くYouTube動画3本。「いつ、どこに、どんな月が見える」問題を得意にすれば、月は何とかなる。演習問題集の練習問題4のグラフ読み取りはよく出る。5も、おなじみ。よく出る問題も参考にしよう。
第16回 気体⑴
1.ヒトの生活と気体
2.気体の集め方
3.気体の性質と作り方
授業動画は、気体の「酸素」「二酸化炭素」「アンモニア」。覚える部分も多く、気体暗記カード(web)も活用しましょう。
第17回 気体⑵
1.水素の発生
2.二酸化炭素の発生
3.酸素の発生
授業動画は、気体の「水素」。計算がポイントになるので、よく出る問題「水素」なども見ておこう。演習問題集の基本問題と練習問題は、この単元を代表する良問。できるようにしたい。発展問題も、よくある応用。力がある子は、挑戦してほしい。
第18回 植物のはたらき
1.光合成
2.呼吸
3.光合成と呼吸
4.植物と水
授業動画は、植物の「光合成」「植物(水の通り道・蒸散)と顕微鏡」。基本的知識を理解して、蒸散の計算ができれば良し。
第19回 地球
1.地球のようす
2.地球の歴史
3.地球上の位置
時差は、YouTube動画「時差計算」を見よう。地球の歴史は、入試ではあまり出ない。古生代(三葉虫)、中生代(恐竜・アンモナイト)、新生代(マンモス)程度で良い。
4年(下)
第1回 ヒトのからだ
1.骨と筋肉
2.呼吸
3.消化
4.血液の流れ
5.感覚器官
すべて、人や動物の体。
よく出る問題(基本)よりも、もっと基礎的な知識が問われる。自分のからだにあてはめ、おもな内臓の働き、動脈と静脈のちがいなどを理解しておこう。目や耳や歯など、細かい部分も見ておこう。
第2回 秋の生物
第3回 電気⑴
第4回 電気⑵
1.回路図のかき方
2.かん電池のつなぎ方
3.豆電球のつなぎ方
4.いろいろなつなぎ方
すべて、豆電球とLED。豆電球①を見ておく。乾電池の並列が混乱するので、「乾電池の並列つなぎ」(YouTube動画)も見ておく。
第6回 物の溶け方⑴
第7回 物の溶け方⑵
第8回 流水と地形
第9回 ばね
第11回 月
1.月のようす
2.月の満ち欠け
3.月が満ち欠けする理由
4.月の動き
すべて、月。
動画「月①」を見て、付属のチェックテストを解いておこう。YouTube動画「なぜ月の出は毎日50分おそくなるのか」も見ておこう。
第12回 いろいろな気体
第13回 物の燃え方
第14回 音
第16回 冬の生物
第17回 水溶液の分類
1.解けている物の状態で分ける
2.においの有無で分ける
3.水溶液の性質で分ける
4.水溶液の分類のまとめ
すべて、酸とアルカリ・中和。
動画「酸性・中性・アルカリ性」を見て、よく出る問題(基本)を解いておこう。
第18回 棒のつり合い
5年(下)
第1回 生物のつながり
第3回 水溶液の中和
1.水溶液の分類
2.酸・アルカリ水溶液の中和
3.中和の計算
すべて、酸とアルカリ・中和。
中和の計算も、パターン化されています。2種類の固体が残る計算がポイントになるので、よく出る問題でしっかり練習しよう。
第4回 ヒトと動物の消化・吸収
1.食物と養分
2.消化
3.養分の吸収
4.動物の消化器官
すべて、人や動物の体。
動画「人体(消化と吸収)」のだ液実験は重要。「魚の体」も見ておこう。
第6回 ヒトと動物の呼吸・循環
1.人の呼吸
2.人の心臓と血管
3.血液の循環
4.いろいろな動物の血液循環
すべて、人や動物の体。
動画「呼吸と気体検知管」「人体(心臓と血液循環)」「魚の体」を見ておこう。心臓がポイント。暗記ではなく、血液の流れを意識して、理屈で理解しよう。呼吸のまとめとして、「動物総合(イカ解剖)」も余裕があればチェック。
第7回 物の燃焼
1.物の燃焼
2.いろいろな物の燃え方
3.金属の燃え方
4.金属のさび
すべて、燃焼。
よく出る問題で、基本の知識を確認しよう。金属の一部燃焼計算、マグネシウムと銅の燃焼計算も練習しよう。余裕があれば、金属燃焼の鶴亀算も。
第9回 流水と地層
1.流水の働き
2.地層
3.堆積岩
4.化石
すべて、流水・地層・岩石。
流水の働きは、流速のグラフが出やすい。動画「流水の働き」に問題が載っているので、練習しよう。地層は、傾きの問題がポイント。よく出る問題で、コツをつかんでおこう。
第11回 光と音
第12回 火山と地震
1.地球のつくりと火山
2.火山の噴火
3.火成岩
4.地震
1~4は、地震・環境問題。
地震は、起こる仕組みや、計算問題が問われます。練習しておこう。
第13回 生命の誕生
第14回 電流と抵抗
1.乾電池のつなぎ方
2.豆電球のつなぎ方
3.スイッチのある回路
4.電熱線と電気抵抗
5.電熱線と発熱
1~3は、豆電球。4・5は、磁石・電磁石・モーター・コンデンサ・電熱線。
豆電球はスイッチの問題、電熱線は、電流や発熱の問題を、よく出る問題で練習しよう。電熱線の発熱は、熱=電琉×電圧でも、熱=電流×電流×抵抗でもよいので、自分が使いやすい方法で解いてください。
第16回 電流と磁界
1.方位磁針のふれと電流
2.磁針におよぼす力の大きさ
3.電磁石
1~3は、磁石・電磁石・モーター・コンデンサ・電熱線。
自分で手を動かして、方位磁針のふれの向き、電磁石の極などを決められるようにしよう。モーターの回転する理由は、動画を見て理解しよう。
第17回 太陽の動き
1.太陽のようす
2.太陽の1日の動き
3.太陽の1年の動き
4.日影曲線
1~4は、太陽と地球。
日本での太陽や影の動き(天球図・日影曲線)を、頭の中で思い出せるくらい理解すること。南中高度計算対策で、動画「緯度と南中高度」、緯度と昼間の長さ対策で、動画「地球と月の公転」を見ておく。また、応用で、日本以外の太陽の動きも出ます。動画「世界各地の天体の動き」は必見。
第18回 太陽と地球
1.日の出と日の入りの時刻
2.昼の長さと南中高度
3.地温・気温の変化
1~4は、太陽と地球。
日の出・日の入り・南中時刻の計算を、完璧にする。問題は、パターン化しているので、よく出る問題を解ければOK。応用として、透明半球の計算や昼と夜の領域問題が出ます。生徒の質問もやっておこう。
6年(上)
1.植物の分類とつくり
2.植物の成長
3.植物のはたらき
4.植物と環境
植物の総まとめで、目標は典型問題の完成。まずは、演習問題集を解きます。基本問題、練習問題ともに、よく出る良問です。できなかったところは、メイン教材や授業動画で勉強しましょう。
授業動画は、すべて、植物。「花のつくり①②」「光合成」「植物(水の通り道・蒸散)」は特に重要です。
1.地球
2.太陽
3.月
演習問題集の、基本問題6,練習問題の1~7は、よく出る良問です。特に、練習問題の6と7は、できるようにしたい。発展問題も、有名な問題なので、余裕があれば挑戦したい。
授業動画は、太陽と地球の、「太陽と気温(南中高度)」「太陽と影の動き」「地球と月の公転」など。発展問題は、「昔の人は地球・太陽・月の大きさをどのようにして求めた?」を参考にしましょう。
1.電流と抵抗
2.電流と磁界
演習問題集の基本問題と練習問題は、全部、よくある良問。範囲が広いので、理解度が低い単元を中心に勉強したい。多くの子は、電熱線の発熱で混乱します。
授業動画は、磁石・電磁石・モーター・発電・電熱線の、「電流と磁界」「電熱線と電流」「電熱線と発熱」が中心。よく出る問題に類題もあるので、弱点補強に利用したい。
1.星座と星
2.太陽系の星
演習問題集の狙いは、星や星座の名前、星の動きの計算、星座早見の使い方、黄道12星座あたり。まだ、金星や火星、南半球から見た天体は、深入りしていない。
授業動画は、星の「夏の星と流星群」「冬の星」「星座早見」「星の動き」。また、黄道12星座は、金星・火星・黄道12星座の「黄道12星座」「太陽系の惑星」。
1.無セキツイ動物
2.セキツイ動物
3.動物と環境
動物の総まとめで、目標は典型問題の完成。まずは、演習問題集を解きます。基本問題、練習問題ともに、よく出る良問です。できなかったところは、メイン教材や授業動画で勉強しましょう。
授業動画は、昆虫は、「アゲハとモンシロチョウ」「昆虫①②」。セキツイ動物は、人や動物の体の「動物総合」。YouTube動画の「ベルグマンの法則」「池のメダカの数え方」も参考になります。メダカの泳ぎ方実験は、メダカとプランクトンの「メダカ」にあります。見たことがない人は見てください。
1.物の運動
2.てこのつり合い
運動は、どの条件で決まるかを読み取れるようにする。具体的には、振り子の周期は、振り子の長さだけ。速さは、高さだけ。衝突のエネルギーは、高さ(速さ)と重さだけ。
てこは、算数の図形問題と同じように、条件や、出した答えを図に書き込んでいくのがポイント。
演習問題集の基本問題と練習問題が解ければすごい。
授業動画は、振り子と運動は、すべての動画が対象。イメージが立ちにくいところは実際の実験で見ておこう。よく出る問題も使えます。
てこは、授業動画も使えるが、よく出る問題に、あなたができなかった問題と似たものがあると思います。弱点補強に使いましょう。YouTube動画「積み木」も参考になる。
1.気体の性質
2.気体の発生
3.金属
基本の知識を理解して、計算ができるようにする。どうしても計算に目が行きがちだが、実際の入試での出題割合は、知識の方が多い。
気体のつくり方と性質は、気体の各動画で理解しておこう。「身近な化学」「気体の発見」YouTube動画の「空気をパンに変えた人たち」も、ぜひ見てね。計算問題は、「よく出る問題」に類題がたくさんあるので、練習してください。
1.ヒトのからだと誕生
2.ヒトと環境
演習問題集の狙いは、基本知識の定着と、呼吸と血液の典型計算の完成と、胎児。
授業動画は、人と動物の体の「骨と筋肉」「呼吸と気体検知管」「人体(消化と吸収)(心臓と血液循環)」「動物の体の工夫(鳥・胎児)」。YouTube動画の「胎児の心臓と血液」も役に立つ。
1.気象の観測
2.天気の変化
演習問題集の狙いは、基本知識の定着と、雲画像と天気図から天気の変化や季節を読み取ること、湿度計算ができることの3点。
授業動画は、風と気圧・天気と湿度の「風と台風」「天気の変化」「湿度」。よく出る問題も、類題が多いので見ておきたい。
6年(下)
有名校対策
1.光合成
2.発芽
3.蒸散作用
4.花
すべて、植物。よく出る問題の基本問題ができればOK。
1.太陽の動き
2.月の満ち欠け
3.星の動き
4.日食
1.4は、太陽と地球。透明半球や日影曲線を練習する。日食と月食は、いろいろな問題が出ます。動画「日食と月食」は必見。
2は、月と金星・火星・黄道12星座。月は、よく出る問題(基本)を解き、余裕があれば、金星と黄道12星座の基本を練習しておこう、
3は、星。星の動きの計算ができるようにしておく。よく出る問題を解けばOK.
生徒の質問をチェック。
1.豆電球の回路
2.スイッチのある豆電球の回路
3.電熱線
4.電流と磁界
1・2は、豆電球・LED。よく出る問題の基本をやろう。スイッチ問題は、豆電球1個の回路、2個の回路と順に考えればできる。解きなれておこう。
3・4は、磁石・電磁石・モーター・発電・コンデンサ・電熱線。よく出る問題(基本)で練習しておく
1.気体の性質
2.酸素の発生
3.二酸化炭素の発生
4.水素の発生
すべて気体。よく出る問題で、気体の製法と性質を確認し、典型的な計算を練習すること。
1.動物の分類
2.動物のからだ
3.昆虫
4.メダカ
1・2は、人や動物の体の「動物総合」。まずは、動物総合(イカの解剖)で、せきつい動物の分類をしっかり理解。
3は、昆虫。
4は、メダカとプランクトン。
1.気温と湿度
2.台風
3.気象現象
4.日本の天気
すべて、風と気圧・天気と湿度。
台風は、よく出ます。よく出る問題で確認しておこう。
1.ろうそくの燃焼
2.金属の燃焼
3.水の状態変化
4.熱の伝わり方
1・2は、燃焼。
3は、水と氷と水蒸気・三態。
4は、熱の伝わり方(伝導・対流・放射)。
よく出る問題(基本)が解けるようにする。燃焼については、計算問題が出るので、余裕があれば、よく出る問題(応用)もやっておこう。
難関校対策
1.太陽の動き
2.星の動き
3.月の満ち欠け
4.日食
5.惑星
1.4は、太陽と地球。世界各地の天体の動き、地球と月の公転も見ておこう。
3・4は、月。月から見た地球は必見。よくある問題(応用)も頻出。
2は、星。
5は、金星・火星・黄道12星座。合と衝の計算が頻出。生徒の質問をチェック。
1.豆電球の回路
2.スイッチのある回路
3.電流と磁界
4.電熱線の発熱
5.電磁誘導
1・2は、豆電球・LED。よく出る問題をやっておく。直列と並列の混合回路も、できるように。
3・4・5は、磁石・電磁石・モーター・発電・コンデンサ・電熱線。電熱線と発電は、よくある問題と生徒の質問で練習しておく。
1.気体の性質
2.水素の発生
3.二酸化炭素の発生
4.酸素の発生
5.中和した水溶液と金属の反応
すべて気体。身近な化学、気体の発見も見ておこう。よくある問題で、計算問題を練習しよう。
1.雲のでき方と台風
2.前線と天気
3.気温と湿度
4.異常気象
5.気団と前線
すべて、風と気圧・天気と湿度。
台風についての問題が多い。梅雨と秋雨のちがい、線状降水帯なども、動画で確認しておこう。
1.ものの燃え方
2.アルコールの燃焼
3.気体の燃焼
4.水の状態変化
5.熱の伝わり方
1・2・3は、燃焼。よく出る問題(応用)の計算を練習する。
4は、水と氷と水蒸気・三態。
5は、熱の伝わり方(伝導・対流・放射)。