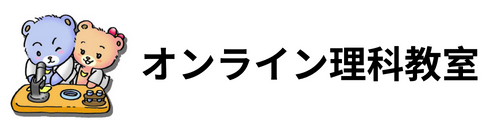6年(Ⅳ)
第19回 植物① 植物のつくりとはたらき
<内容>
1.種子のつくり
2.発芽と成長の条件
3.蒸散と呼吸
4.植物のからだのつくり
5.光合成
範囲が広いので、まず栄冠への道の問題を解いて、間違えたところを本科テキストで振り返るやり方がよい。
栄冠への道は、P13~15、P17の2からP21の6まで解ければ問題なし。特にP21の6のグラフは重要。
授業動画は、すべて植物。
<内容と授業動画>1と2は動画「種子のつくりと発芽成長の条件」、3と4は動画「植物(水の通り道・蒸散)、5は動画「光合成」に対応する。光合成グラフ
第20回 植物② 植物どうしのつながりと影響
<内容>
1.花の分類
2.森林の遷移
花のつくりがポイント。森林遷移は軽い扱い。(気候と森林は無視してOK)
栄冠への道は、P31~33、P36~39
授業動画は、すべて植物。
<内容と授業動画>1は動画「花のつくり①②」白黒テキストの図より、実物を動画で見た方がわかりやすいので、絶対に見ること。花のつくりを立体的に理解できる「花のつくりペーパークラフト」もお勧め。2は、動画「森林の移り変わり」。
第21回 動物の特徴とつながり
<内容>
1.昆虫
2.メダカ
3.食物連鎖
4.セキツイ動物
5.顕微鏡
範囲が広く、まずは栄冠への道P50~59をやってみて、理解があいまいなところを本科テキストで見直す。特にP50,51,57の分類問題はできるように。
,<内容と授業動画>
1は、昆虫の、動画「昆虫①②」。2は、メダカとプランクトンの動画「メダカ」。4は、人や動物の体の動画「動物総合」、5は顕微鏡の、動画「植物(水の通り道・蒸散)」または赤ボタンの「顕微鏡」。
第22回 人体①
1.消化
2.心臓と血液
3.肺
栄冠への道P70~79は、よくある良問。特に血管、心臓がポイント。どのように血液が流れ、血管にどのような名前がついているのか理屈で理解すること。また、P74の計算は頻出問題。
<内容と授業動画>
すべて、人や動物の体。1は、「人体(消化と吸収)」、2は「人体(心臓と血液循環)」、3は「呼吸と気体検知管」
第23回 人体②
1.血液循環
2.骨と筋肉
3.胎児
4.腎臓
5.目
栄冠への道P90~95は、できるようにしておこう。特に血液循環は大切。小腸と肝臓のつながりに注目して、いろいろな形の循環図が解けるようにすること。うでの骨のてこ計算も、よく出る。腎臓は、今後、計算問題になっていくので、P95は練習するに値する。目は、基本がわかればOK.
<内容と授業動画>
すべて、人と動物の体。1は、動画「人体(心臓と血液循環)」2は、動画「骨と筋肉」。ただし、うでのてこ計算は、てこの「身近なてこ」の中にもある。胎児は、人や動物の体の。「動物の体の工夫(鳥・胎児)」やYouTube動画の「胎児の心臓と血液」、腎臓は、授業動画は無いが、再吸収計算は、よく出る問題「腎臓の再吸収」にある。目は、今回は知識のみ問われるが、応用になると、動画「両目の立体視(3D)」のような内容になる。
第7回 太陽
1.太陽と地球
2.太陽の動き
3.太陽の位置の表し方
4.地面にできる影
第8回 水のすがた
1.水の蒸発
2.水の沸とう
3.水と氷
4.水の3つのすがた
5.地球上をめぐる水
第9回 光
1.光
2.はね返される光
3.曲げられる光
第11回 植物の成長
1.植物の成長
2.種子でふえる植物
3.親のからだの一部からふえる植物
第12回 植物のつくりとはたらき
1.植物のつくりとはたらき
2.植物のつくり
3.植物のはたらき
第13回 身のまわりの空気と水
1.身のまわりの空気と水
2.空気や水の重さ
3.空気や水をおし縮める
4.空気や水の体積と温度
5.空気や水のあたたまり方
第14回 金属
1.身のまわりの金属
2.金属のあたたまり方
3.金属の温度と体積
第16回 夏の生物
1.夏になると
2.花をさかせる植物
3.実をつける植物
4.昆虫
5.いろいろな動物
第17回 星座をつくる星
1.星座をつくる星
2.いろいろな星座
3.星座早見
第18回 星座の動き
1.星座の1日の動き
2.北極星の見つけ方
3.星座の1年の動き
第19回 動物
1.動物のからだ
2.動物のえさ
3.動物の飼い方